- 2025/02/04
- 田村明孝の辛口コラム
自立した高齢者で、月額25万円程度の厚生年金受給者を入居対象とした、早めの移り住み住宅「サービス付き高齢者向け住宅」(サ付き)は、国交省・厚労省共管事業として、2011年高齢者住い法を改正して、年間300億円の整備費補助を目玉として高齢者住宅業界の耳目を集め、大反響のもとに事業が開始された。
2040年には3921万人に膨れ上がる高齢者に、水回りの整った25㎡(共用の食堂や浴室があれば18㎡)以上の居住空間やバリアフリーの建物、生活相談員を配置し、安否確認体制を整え、従来の有料老人ホームの利用権契約では不安定な居住権利を、賃貸借契約により安定して住み続けられる居住確保、生き生きとした生活を提供する場で健康寿命を延ばし、国にとっては医療費や介護費を削減できると期待され、また事業者には戸当たり100万円の整備費補助や税制の優遇措置を設けた、良いことずくめのサ付き制度が自治体への簡単な登録制としてスタートした。
2011年当時、2006年から始まった総量規制で、介護付有料老人ホームや認知症高齢者向けグループホームの供給が、自治体による規制で急激に減り、もともと不足状態だった特養など介護保険3施設は新規供給が年々減っていて、要介護者が介護施設・介護住宅へ入居したくともできない不足状態が続いていた。
この状況で始まったサ付きは、初年度の登録数約8万戸、翌年度は約5万戸と予想を上回る登録数となり、ブームと言っても過言でないほどの活況を呈した。
サ付きのイメージは「高齢者向けのサービスの付いた施設ではない」住宅と受け取られ、介護状態であっても入居できる施設ではない住宅として捉えられた。
不足状況にあった要介護者の受け皿として入居者を集め、本来の国交省が思い描いていた自立高齢者の早めの移り住みとは真逆の結果となってしまった。
サ付きはその後も供給は増えたが、同様に規制を受けなかった住宅型有料老人ホームも総量規制開始後、介護付有料老人ホームの激減もあり急増した。
不足する要介護者の受け入れ施設は、介護サービスの質に難点はありながらも、サ付きと住宅型有料老人ホームがその受け皿となって行った。
サ付きと住宅型有料老人ホームの供給により、不足状況が改善され、さらに供給過剰状態になる地方も出現し、サ付きは2020年頃から1万戸を下回り、供給は急激に落ち込んでしまった。
サ付きは2024年10月現在約29万戸が供給されている。
ターゲットとした入居者像とは大きく異なり、介護施設と化したサ付きは有料老人ホームと何ら変わるところはなく、今後も要介護者の受け皿として運営を継続していくこととなる。
介護施設不足の穴埋めには役立ったが、サ付きは本来の目的を達成することもなく転機を迎えることとなる。
2011年以前、サ付きの前身「高齢者専用賃貸住宅」(高専賃)は年間供給数1万戸程度であったことを思い返せば、補助金制度がなくなれば、サ付きは年間5千戸にも満たない供給となるだろう。その存在感は薄れ、住宅型有料に吸収されていくだろう。
すでに供給されている29万戸のサ付きは、どのように存在意義を見出していくのかは言うまでもなく、要介護者の受け皿として開設されてきた経緯からしても、今後も引き続き介護サービスを提供する住宅とし存在するしかないだろう。
サ付きを特定施設として運営する介護付有料老人ホームと同様な転換を図るべきである。
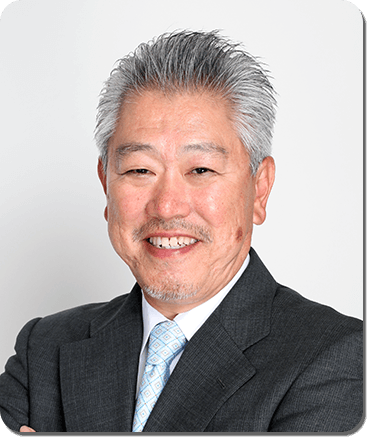
1974年中銀マンシオンに入社、分譲型高齢者ケア付きマンション「ライフケア」を3か所800戸の開発担当を経て退社。
1987年「タムラ企画」(現タムラプランニング&オペレーティング)を設立し代表に就任。高齢者住宅開設コンサル500件以上。開設ホーム30棟超。高齢者住宅・介護保険居宅サービス・エリアデータをデータベース化し販売。「高齢者の豊かな生活空間開発に向けて」研究会主宰。アライアンス加盟企業と2030年の未来型高齢者住宅モデルプランを作成し発表。2021年には「自立支援委員会」発足。テレビ・ラジオ出演や書籍出版多数。

